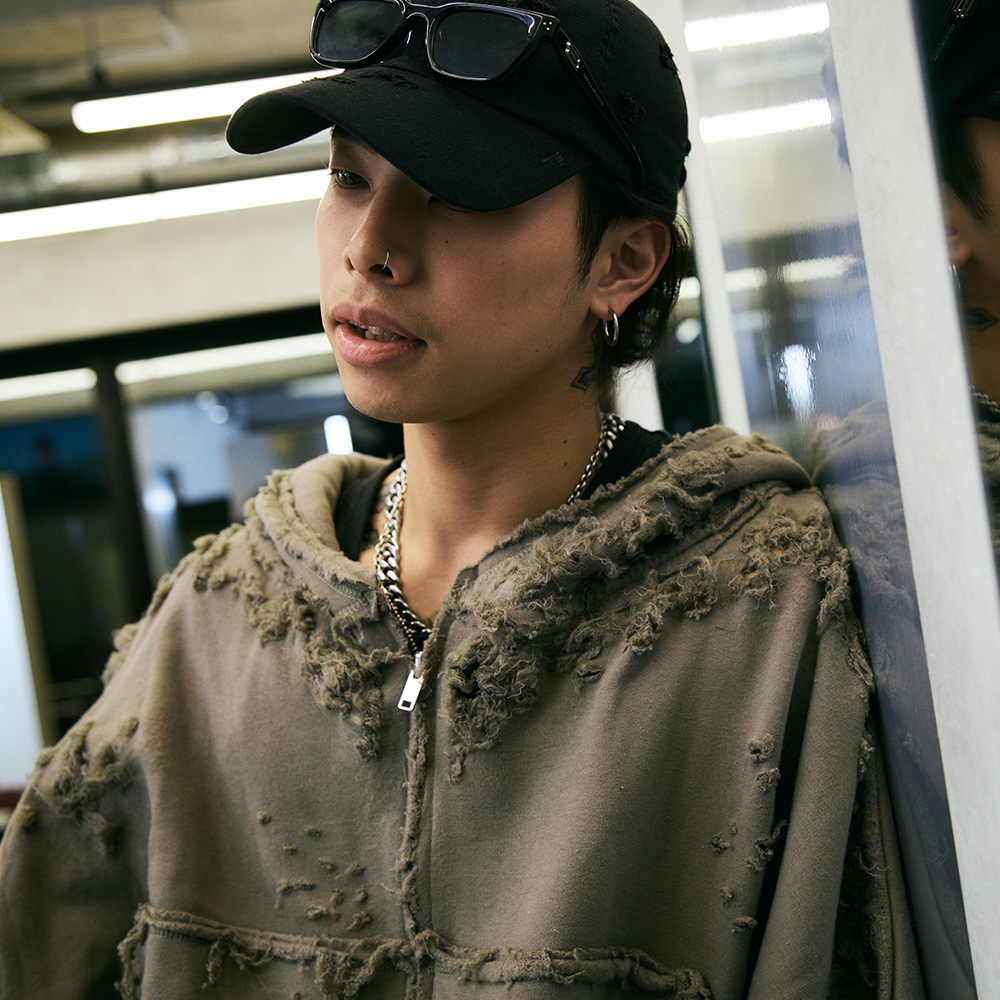パリ。
グラン・アルメ通りに、その秘密拠点はあった。ユダヤ人ボランティアを、イスラエルへと送り込む拠点。ヴィダルが辿り着くと、すぐに検査が始まった。これまでの半生。出身校。軍歴。さらには身体検査もある。それらがすべて終わると書類を渡され、指示が与えられた。
「マルセイユに行きなさい。そこでハイファ行きの船か飛行機を待つんだ」
ハイファ。それはイスラエル北部、地中海に面する港町である。ヴィダルはその街の名前を聞いただけで、こころが奮い立った。
だが、まずはマルセイユである。ヴィダルは南フランスの港町へと向かった。
マルセイユには大きな難民キャンプがあった。『グラン・アナレス・キャンプ』。それは強制収容所から生還してきたユダヤ人たちを収容するキャンプだった。
ヴィダルは初めて、ホロコーストを生きのびた人たちと対面した。その多くは、自らの体験を語らなかった。いや、語らないのではない。語ることができなかったのだ。多くの人が言葉そのものを失ってしまっていた。あまりにも過酷な体験が、こころを壊してしまっていたのだ。
やせこけた身体。落ちくぼんだ目。表情の消えた顔。彼らは“あたらしい国”を建設することを理解していなかった。これから一緒に “あたらしい国”に向かうことすら理解できていなかった。
イスラエルの新政府は、医師や看護師、心理学者たちをキャンプに送り込んでいた。だが、彼らができることはほとんどなかった。まず、体力の回復を待つこと。想像を絶する飢餓状態によって、ちいさく縮んでしまった胃の機能を少しずつ回復させていくこと。ゆっくりと、時間をかけて。医師たちは結局、生還者を見守ることしかできないのだった。
ヴィダルもまた、同様だった。生還者たちを見守ることしかできない。
“あたらしい国”の建設という昂揚感と、人間が人間に対して行ったおぞましい行為への憎悪。こころが引き裂かれてしまいそうな日々。それが結局、5週間もつづいた。その間、ヴィダルはようやくひとりの生還者と話をすることができた。
その男はヴィダルに向かって重い口を開いてくれた。話を始めるとすぐに、男は泣き始めた。ヴィダルの腕のなかに身を投げ出すようにして、泣いた。泣きながら語った。愛するひとり息子が、ガス室へと送られたときのことを。
号泣だった。ヴィダルも泣いた。男を抱きしめながら泣いた。腹のなかではマグマが、音を立ててうねっていた。
あの『ヨム・キプール(※)』の日。シナゴーグで聞いたラビの話は、ほんとうだった。同じように残酷なことが、ヨーロッパ中の収容所で行われていたのだ。
人間とは、こんなにも罪深い存在なのか。人はこころの奥底に、悪魔を飼っているのか。いや人間という存在そのものが、悪魔なのか。
怒りの矛先はまず、ナチスに向かった。だが、あまりにもひどく、むごい現実を繰り返し見聞きしているうちに、その矛先はナチスを飛び越え、人類全体へと向かうのだった。なぜ人は、このような悲劇を見過ごすことができたのか。なぜ、止められなかったのか。
抑えようもない不信感と、同時に無力感が湧き上がってくる。ぼくも、止められなかった人類のひとりだ。
人間は、弱い。どうしようもなく、弱い。圧倒的な暴力には簡単に屈してしまう。想像を超える現実に蹂躙されそうになると、目を閉じる。耳をふさぐ。口を閉ざす。そうやって人は自分を守ろうとする。
だけど、それほどまでに弱い人間がときに戦いを始めることがある。圧倒的な暴力に、立ち向かうこともある。たとえばポーランドのワルシャワで起きた“ゲットー蜂起”のように。
ゲットーとは、ナチスドイツが各地につくった“ユダヤ人隔離地域”のことである。なかでもワルシャワ・ゲットーは最大規模だった。ナチスはまず各地にゲットーをつくり、ユダヤ人を隔離したうえで強制収容所へと送った。
“強制”収容所という名前を、ユダヤ人は誤解していた。当初、ユダヤ人たちは移送される収容所が“強制労働”のための拠点だと思っていた。ところが、次第にそれがユダヤ人を殺戮する“絶滅収容所”だということがわかってくる。事実を知ったユダヤ人たちはさらなる移送を阻止するため、結束して戦うことを決断したのだ。
1943年4月19日。ワルシャワ・ゲットーのユダヤ人は武装蜂起した。貧弱な武器。不十分な補給。それでもユダヤ人は戦った。男性だけではない。女性も戦った。手作りの火炎瓶で、圧倒的な戦力を誇るナチスドイツに挑みかかった。
だが、物量と力量の差は歴然としていた。ドイツはナチス親衛隊(SS)、ドイツ武装警察、さらにはドイツ国防軍まで動員して鎮圧を図る。蜂起軍はそれでも戦った。約1カ月も戦いつづけた。そして、完全に鎮圧された。
ワルシャワのゲットー蜂起。それは世界中のユダヤ人の誇りとなった。
〔われわれはナチスに、ただ蹂躙されるだけではない。武器をとって戦うことができる〕
ヴィダルもまた、そのニュースを知ってこころが震えた。
ユダヤ人だけではなかった。第二次世界大戦中、ナチス占領下のヨーロッパ各国では、多くの抵抗活動が試みられた。“レジスタンス”である。人は圧倒的な力を前にしても、抵抗することができる。屈しないこころを、持つことができる。行動に移すことができる。それもまた一方の真実であった。
人は、弱い。
だけど、人は、強い。
ハイファ行きの順番を待つ間、ヴィダルはさまざまなことを考えた。
差別。偏見。迫害。暴力。屈辱。絶望。そして、かすかな希望。
ハイファに行きたかった。1日も早く、イスラエルへ。そこには希望がある。光がある。未来がある。ユダヤ人の明るい未来がきっと、ある。
ついに順番がやってきた。ハイファ行きの古い軍用輸送機。通称“ダコタ機”。マルセイユからハイファまで、直行することができないオンボロ飛行機。途中、ローマとアテネで二度も給油しなくてはならない。それでもヴィダルのこころは弾んでいた。
光にあふれた街だった。地中海から吹く海風が、砂漠の砂を舞い上げる。だがヴィダルはダコタ機の窓から確かめていた。広大な砂漠のなかに、緑の農場が拡がっていることを。それは入植したユダヤ人同胞が開拓した農場だった。
〔国家をつくらなくては、ユダヤ人はいつか存在しなくなる〕
〔ホロコーストの現実を見つめよう。次はもっと恐ろしいことが起きるかもしれない〕
それがユダヤ人の合い言葉だった。とくにイスラエルへやってくる世界中のボランティアたちは、その思いを強く共有していた。
第二次世界大戦の前から、ユダヤ人の入植は始まっていた。ユダヤ人は“キブツ”という名の集産主義的共同体をつくり、砂漠を開墾した。そこにボランティアが加わっていく。
ハイファの地を、ヴィダルは踏みしめた。一歩踏み出すごとに、感動で震えた。
〔今、まさにぼくは歴史をつくる現場に立っている〕
〔メディカルセンターへ集合せよ〕
それが到着後、最初の指示だった。何百人ものボランティアがハイファのメディカルセンターに集まった。
行われたのは医師による身体検査である。
ヴィダル・サスーン。
年齢:20歳
身長:5フィート10インチ(177.8cm)
体重:11ストーン6ポンド(69.85kg)
その他さまざまな身体能力の検査を含め、結果は“A-1”。トップランクでの合格だった。
「君は海外ボランティア隊に入りたいかね?」
医師が聞いた。
ヴィダルは即答した。
「いいえ。私はパルマッハに参加したいのです」
パルマッハ。それはヘブライ語で“突撃隊”という意味の武装組織である。イスラエル独立前には“キブツ”の防衛にあたっていたが、第一次中東戦争(イスラエル独立戦争)が始まると、戦闘の中心部隊として活躍する。
ヴィダルは“キブツ”の労働者として建国に参加するのではなく、一兵士として建国を成就する道を選んだ。それこそが、あやふやなアイデンティティーを確立する唯一の道だと信じていた。
パルマッハに入隊すると、すぐに3人の“同期”とともにチームが編成された。米国からやってきたシミー。オーストラリア生まれのジャック。そして共にファシストと戦った“43グループ”時代の仲間、コリンである。
チーム編成が終わると、すぐに基礎訓練が始まる。4人はパルマッハのキャンプに送り込まれた。
起床は6時半である。昼間は徹底した戦闘訓練。まずはマーシャルアーツ。一対一で組み合って戦う格闘技。さらに武器の取り扱い。拳銃、小銃、ライフル、手榴弾。明るいうちに射撃訓練を終えると、もうクタクタになっている。
消灯は21時。掘っ立て小屋のベッドに身を投げると、すぐに睡魔がやってくる。だが、戦場はぐっすり眠れるような場ではない。夜中の2時に叩き起こされて、ウォーキングとランニングである。ただのウォーキングではない。数十キロの荷物を背負っての行軍訓練だ。その行軍がやがてランニングに変わる。背中に荷物。手には銃。列を乱さぬよう、走る、走る、走る。ベッドに戻るのは3時半。そしてまた6時には叩き起こされる。それが日課だった。
丸2カ月。ヴィダルは耐えた。それまで経験したことのない過酷な訓練に耐えた。チーム全員で、耐えた。
基礎訓練が終わると、ヴィダルたちはバスに乗せられ、いくつかのチームとともに北部へと向かう。ネゲブという街で“第三大隊”に合流。そこから先は、本物の“戦場”だった。
ネゲブに到着した日の夜、ヴィダルたちは目的地である『ニル・アム』という名のキブツへと向かう。
まず、40人から50人のグループを編成。それを偵察隊が先導して『ニル・アム』をめざす。道中は、アラブ側の支配地域。どこにアラブ兵が待ち構えているかわからない。
指示されたのはわずか二言。
「アラブ語が聞こえたら、静止」
「合図が出たら、前進」
深夜の行軍が始まった。砂地の上に灌木が茂っている。その間を縫うように進む。足音は最小に。
そうか、とヴィダルは思った。あの過酷な訓練はこのためだったのか。
しかし、ヴィダルの発想は甘かった。後に遭遇することになる危機。命の危機。そのときこそ、あの過酷な訓練の真価が発揮されるのであった。
突然、前を行くコリンが止まった。ヴィダルはぶつかりそうになる。と、ヴィダルの耳にかすかな声が飛び込んでくる。
アラブ語だ。
ヴィダルは氷像のように身体を固める。息も止める。だが、身体の内部の動きは止められない。カッと熱くなる。アドレナリンが噴き出す感覚を、初めて味わった。
やがて、合図。前進だ。
いつ射撃されるかわからない。そんな緊張感は初めての体験だった。再び、アラブ語。静止。そして前進。
繰り返すうちに、ヴィダルは興奮状態になっていく。噴き出すアドレナリンに、恍惚感さえ覚える。
〔まるで映画の一シーンみたいだ〕
そんな言葉が脳をよぎった。だが、すぐに思い直す。この銃には実弾が込められている。撮影のために空砲を撃つわけではない。これは実戦なのだ。
1948年6月11日から始まった4週間の“休戦”。その間を利用して、イスラエル軍は“パルマッハ”を含む武装組織を統合し、“イスラエル国防軍”を編成した。さらにチェコスロバキアから戦闘機(メッサーシュミットBf109)を買い入れ、M4中戦車を世界中からかき集めた。
イスラエルには武器の供与が認められていなかった。だからM4中戦車は「スクラップにして鉄材を得る」という名目で入手。再生しては前線に投入していくのだった。
また、兵士の供給も急務だった。イスラエルは、ヴィダルたちと同じ方法で多数の兵士を訓練し、前線へ送った。40人から50人のグループを、何回も、何十回も、何百回も送り出し、夏から秋にかけて合計数万人にも達する兵士たちを前線のキブツに送り込んだのである。
さて、前線に無事到着したヴィダルは、すぐに戦闘に加わった。最初の実戦。それは丘の争奪戦だった。
当初、ヴィダルたちは優勢だった。目標の丘に駆け上がり、アラブ兵を追い回した。逃げ惑うアラブ兵。丘の制圧は目前だった。ところが、そこにエジプトの装甲車が現れる。頑丈な鉄板で覆われたクルマが、ヴィダルたちに向かってきた。
イスラエル側には武装車がなかった。小銃ではまったく歯が立たない。だから今度はヴィダルたちが逃げる。逃げ回る。事件はそのとき、起きた。
バチッ。
ヴィダルの腰のあたりで音がしたかと思うと、戦闘服のズボンがずり落ちた。あわてて左手でズボンをつかまえる。右手には銃。
痛みはなかった。おそるおそる視線を落とす。血は噴き出していない。
ベルトだった。何かの拍子にベルトが切れたのだ。
焦った。一個小隊44人のうち、43人はどんどん先へ逃げていく。ひとり、ヴィダルはズボンをつかみ、銃を抱えながら追いかける。
銃は貴重だった。だから絶対に手放すわけにはいかない。43人は5ヤード先を駆ける。ヴィダルも駆ける。背後からは装甲車。顔面蒼白。息絶え絶え。それでも駆ける。必死で走る。まさに命がけ。訓練の成果はそこで、発揮されるのであった。
駆け抜いた。先に陣地へと駆け込んだ43人から遅れること12秒。ヴィダルも安全地帯に、転がり込んだ。
すぐに味方の反撃開始。装甲車は、あわててUターンして走り去っていった。
「くっくっくっ」
コリンがついに笑いを抑えられなくなった。それが契機となり、ヴィダルの“英雄的行為”は、陣地を笑いで満たした。その“事件”が、結果的に隊の結束を生み、仲間意識を醸成することになる。
だが“事件”はすぐに他の小隊にも広まり、それから約1カ月もの間、顔見知りではない兵士もヴィダルの顔を見るだけで笑い出すことには閉口したが……。
つづく
【ヨム・キプール】Yom Kippur
贖罪の日。ユダヤ教における最大の休日のひとつ。徴兵され、英国空軍に入隊したヴィダルはその日、自宅に帰って祝うことを許された。そこで母を伴い、ユダヤ教の会堂である“シナゴーグ”へ向かい、ホロコーストの生還者の話を聞いた。(第21話参照)
☆参考文献
『ヴィダル・サスーン自伝』髪書房
『Vidal Vidal Sassoon The Autobiography』PAN BOOKS
『ヴィダル・サスーン』(DVD) 角川書店
『夜と霧』ヴィクトール・E・フランクル著 みすず書房
『イスラエル建国の歴史物語』河合一充著 ミルトス
『アラブとイスラエル』高橋和夫著 講談社現代新書
『私家版・ユダヤ文化論』内田樹著 文春新書
『アメリカのユダヤ人迫害史』佐藤唯行著 集英社新書
『ヴェニスの商人』ウィリアム・シェイクスピア著 福田恆存訳 新潮文庫
『物語 エルサレムの歴史』笈川博一著 中公新書