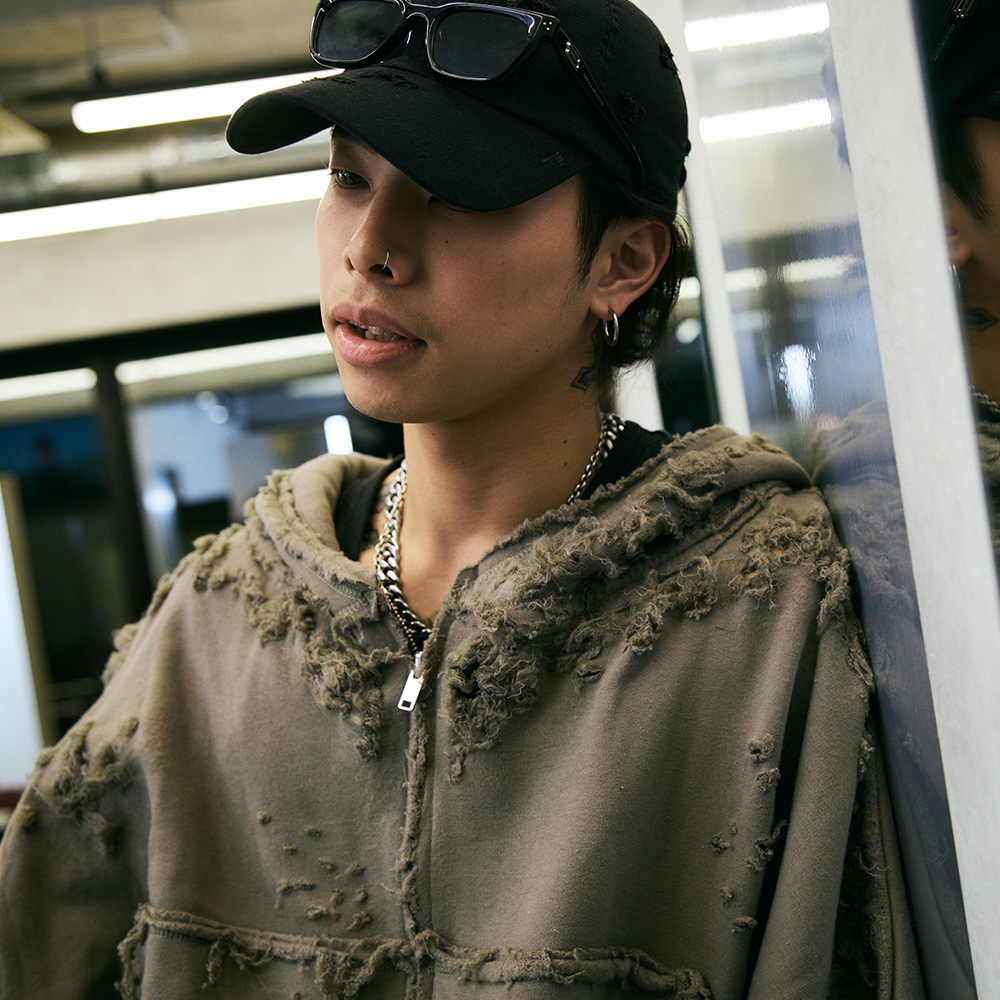バスに乗り込んでも、英語クラブのメンバーはみな無口だった。つい最近まで敵国だったアメリカ。これからその基地へ行くのだ。アメリカ軍のド真ん中へ。そこでいったい何が待っているのか。みな戦々恐々である。
基地の入口に到着した。バスはいったん止まり、衛兵のチェックを受けた後に基地のなかへと滑り込んでいく。周囲は軍服に身を包み、小銃を肩から下げた兵士ばかりである。
やがてバスは白く大きな建物の前で止まった。建物の入口には大柄の女性が立っていた。
大野は先頭を切ってバスから降りた。だが他の生徒たちはつづかない。大野は勇気を奮って、大柄の女性にあいさつをした。もちろん英語で。すると女性は目をまん丸にして驚いた。
「Amazing!」
またこれである。日本人の高校生が英語を話す。それだけでアメリカ人にとっては驚きなのだ。
大野たちをバスに乗せて、ここまで連れてきてくれた赤十字の女性が紹介してくれる。
「こちらはメアリー。この小学校のschoolmistressです」
大野は「schoolmistress」という言葉の意味がわからなかった。
「schoolmistress?」
聞き直す。
「Yes, schoolmistress. It mean ….so…. schoolmaster. 」
(あ、ほうか。校長か。校長先生の女性名詞なんや)
そこまで理解して、思わず日本語で言った。
「えっ、校長? 女が?」
信じられなかった。アメリカは女の人が校長になれるのか。
大野は校長と紹介された女性をまじまじと見つめた。校長はニコニコしている。
(ほうか。これが男女平等っていうことなんか。男女平等になったら、女の人でも校長になれるんか。偉くなれるんか)
たいへんなカルチャーショックだった。たしかにあたらしい憲法は男女の平等を掲げていた。だが、それは本の中でのこと。文字で表わされた概念でしかなかった。しかしこうして目の前に、男女平等の実例が現れるとさすがに動揺してしまう。
(ってことは日本の学校でも、これから女の校長が出てくるっていうことなんやろか。ほんとうにそうなんやろか。そんなことがあり得るんやろか)
大野にはどうしても信じられなかった。
バスからはようやく、英語クラブのメンバーたちが降りてくる。大野はメンバーに紹介した。
「こちらが校長先生のメアリーさんやと」
メンバーは大野と同様、みな驚いた表情になった。
「さぁ、いらっしゃい。学校のなかを見せてあげます」
メアリー校長は大野たちを促して建物のなかへ連れて入った。
教室では、小さな子どもたちが十数人、授業を受けていた。その光景を見て、大野はまた驚く。そのなかに黒人の子どもが何人もいたのだ。
(白人と黒人が同じ教室で授業を受けるんや)
大野たちが教室に入っていくと、子どもたちはみな振り返り、驚いた表情になって見つめてきた。メアリーは、やさしい笑顔で語った。
「みなさん、今日はここに日本人のおにいさん、おねえさんが来てくれました。みなさんはいま、日本に住んでいます。だからね、これから日本人ともお友だちになっていかないといけないんですよ」
メアリーは一生懸命、語った。だが、生徒たちの表情は変わらなかった。驚きと警戒。
(そりゃそうやわ)
大野は思った。
(もし逆の立場やったら、オレたちもっと警戒しとるわ)
つづいてメアリーは、大野たちを大きな部屋につれていった。そこは食堂のようだった。
赤十字の女性が待っていて、大野たちを席につかせると話し始めた。となりには日本人の若い男がいる。どうやら通訳のようだ。
「みなさん、今日は私たちのキャンプに来てくれてありがとう。私たちは心から歓迎します。まずはここでくつろいでくださいね」
赤十字が話し終えたころ、数人の兵士が金属製のお盆を持って入ってきた。
「ここは将校たちがお酒を飲んでくつろぐ部屋です。みなさんにもビールくらい出してあげたいところですけど」
そう言って赤十字は片目を閉じ、つづけた。
「そういうわけにもいかないから、今日はティーで我慢してくださいね。おつまみはアメリカンクッキーをお出ししますからね」
通訳はそう訳した。大野はすべて、英語で理解していた。ただ、アメリカンクッキーというものが、どのような“おつまみ”なのかがわからなかった。
「アメリカンクッキーって、なんですか?」
大野は英語で聞いてみた。赤十字は少し考えた。
「うーん、そうね。そう、ビスケット。ビスケットって言えばわかるかしら?」
ビスケットは知っていた。お菓子だ。チョコレートとガムとビスケット。それは米軍が日本を占領して以来、子どもたちが真っ先に覚えた英語だった。だけど大野は食べたことがない。
テーブルには紅茶と、ビスケットが並んだ。なんともいえない香りが漂ってきた。あまい香りだ。
「さぁ、どうぞ。みなさん、召し上がれ」
メンバーたちは顔を見合わせたまま動かない。そこで大野が最初に手を伸ばした。もちろんビスケットに。
おいしかった。口のなかに香りがひろがり、舌の上で甘さがとろけた。世の中に、こんなにうまいものがあるのか。大野の意識は陶酔の世界に漂った。
結局、ナマの英語に触れる機会は多くはなかった。しかも大野以外のメンバーはだれひとりとして、一言たりとも英語をしゃべることはなかったし、意味を理解できなかった。だが帰りのバスのなかは、行きとは打って変わって騒然としていた。赤十字は同じバスで、大野たちを学校まで送り届けてくれたのである。
「すごかったなぁ」
「うまかったなぁ」
「大野はすごいなぁ」
「なんで英語、しゃべれるんや」
みな口々に体験を語る。軽い興奮状態である。
メンバーの印象に残ったのは、紅茶とビスケットのようだった。もちろん大野のなかにもその味は強い印象が残っている。ただ、それ以上に驚いたのが「平等」という概念だった。アメリカでは女性も、黒人も、分け隔てなく生きている。それが強く、強く印象づけられたのだった。
米軍基地の訪問から1週間が経った。その間、大野はずっと考えつづけていた。
(お礼に行かないかんのやないか)
あれだけ歓待してくれたのに、オレたちはお礼にも行ってない。そこで大野は、木暮に相談してみた。あの同志社出の英語教師である。
「先生、一緒にお礼に行きましょう」
すると木暮は驚いたような表情を見せながら言った。
「いや、オレはええわ。おまえ、ひとりで行ってこやあ」
(行ったほうがええ)
心のなかの、大野が勧めた。
(行ったら、もしかすると潜り込めるかもしれん)
じつは真剣に考えていたのだ。アメリカ軍の基地で働く。
基地にはさまざまな仕事があった。しかもそこではすでに多くの日本人が働いていた。コックがいた。理容師もいた。倉庫係もハウスボーイもいた。コックや理容師は資格がないと無理である。だけど倉庫係やハウスボーイにならなれるのではないか。そう考えていたのである。
働くことができれば、もっと英語がうまくなる。勉強できる。
しかし、それは甘い幻想でしかなかった。基地で働くにはとくべつなツテが必要だと言われていた。しかも求められるのは英語を学ぶ人ではなく、英語ができる人。
英語ならできる。少しは……。そう思っていた。だけどそれをどう証明すればいいのか。どうやったら働き口を見つけられるのか。どうやったらツテをつくれるのか。まったくわからなかった。だけどお礼に行くことで、もしかすると何かが動くかもしれない。
(ほうや。とにかく自分が動いてみよ。基地にお礼に行ってみよ)
放課後、大野は電車で基地へと向かった。旧大日本帝国陸軍各務原基地。それがそのままアメリカ陸軍『キャンプGIFU』となっている。その入り口のゲートまでたどり着いた。さて、どうするか。
大野はゲートの前で立ちすくんだ。アポイントなど取っていない。電話もしてない。電話番号も知らない。知っているのは校長先生の名前だけ。たしかメアリーだった。
ゲートには衛兵がいた。ヘルメットの下から、こっちを見ている。
(わっ。どうしよう)
高校の、制服姿の大野はどうしようもなく目立っていた。
「Hey , boy !」
大きな声が耳に突き刺さった。振り返ると軍服の胸が間近に迫っていた。見上げると黒人。大野は思わずその場で飛び上がりそうになった。しかし瞬時に軍服の胸や肩章を確認する。それは戦時中に徹底して叩き込まれた習性だった。
憲兵。伍長。
読み取った。
憲兵とはMP=ミリタリーポリス。軍隊のなかの警察だ。
伍長。兵卒の上、下士官の一番下だ。
「おまえ、なにやってんだ」
<What are you doing ?>
大野は覚悟を決めた。
「連隊長に会いたいんです」
<I want to see your Base Commander.>
「なんだって?」
<What ?>
憲兵伍長は驚いた。なに言ってんだ、この日本人のハイスクールボーイは。なんで我らが連隊長に会いたいと言うのか。
「なんで会いたいんだ」
「私の名前は大野です。先週、アメリカの赤十字から招待されてここに来たんです。アメリカンスクールで歓待してもらったから、お礼に来たんです」
なんとか英語で言った。憲兵伍長は少し考えていたが、こう言った。
「ちょっと待て。連隊本部に電話するから」
衛兵の詰め所に向かった憲兵伍長は、ほんの数分で戻ってきた。
「ここで待ってろ」
ほどなくしてジープがやってきた。運転しているのは白人だった。大野は階級をチェックした。大尉だった。
憲兵伍長は大尉に最敬礼である。なにしろ階級で十個以上もの差がある。すぐにゲートは開かれた。
「さぁ、乗って」
<Would you ride on ?>
「ありがとうございます」
<Thank you , sir>
ジープは連隊本部の建物の前に停まった。白人大尉は大野を伴って、連隊長室へ入っていく。部屋に入るなり、白人大尉は最敬礼である。その相手、奥からこちらへ歩いてくる連隊長を見て大野は思わず「えっ」と声を出しそうになった。連隊長は黒人だったのだ。階級章を見ると中佐である。白人大尉のさらに2つ上。
そのとき、大野ははっきりとわかった。『平等』の、ほんとうの意味が。
(アメリカってすごい国やな)
それは衝撃だった。
(がんばれば、上に行けるんや。だれでも偉くなれるんや。たとえ黒人やったとしても)
黒人は、下の階層の人種だと思っていた。いや黒人だけではない。アジアの人々も同じだ。白人だって「米英人は鬼畜」と教わってきた。世界の中で最も優秀な民族は日本人。軍国少年はそう信じて疑わなかった。そう信じるよう教育されてきた。学校のなかだけではない。家庭でも、地域社会でもそれが当たり前だった。異議を唱える者などいなかったし、もし唱えていたらそれこそ憲兵に拘束されていただろう。差別は、ごく自然のことのように当時の日本に根をおろしていた。だからこそ大野は驚いたのだ。黒人の上官に、白人の副官が最敬礼している。白人の返事はつねに「イエッサー<Yes , sir>」である。
その連隊長が、両手を拡げて大野を迎えてくれた。
「Mr.Ohno , Why did you come hear , today ?」
<大野さん、今日は何しに来たのかな?>
大野の肩を叩きながら、笑顔で問いかける。
「えっ?」と、大野はまた驚いた。
(ミスターオオノ、と。いま連隊長はオレの名前にミスターをつけてくれた。なんてことだ。連隊長が、やぞ。オレにミスター、やと)
そう思いながら答えた。
「先週は私たちを歓待してくださって、ほんとうにありがとうございました。今日はそのお礼に来ました」
「なんだ、それでわざわざ来てくれたのかい。それはありがとう」
そう言って、連隊長はつづけた。
「で、なにかあるんだろ?」
<Do you have anything happen ?>
連隊長は言うのだ。おまえ今日ここに来たからには何か考えてることがあるんだろう?
見透かされていた。大野の下心。就職のお願い……。大野は迷った。
会話が途切れたのを、連隊長は「英語」のせいだと思った。
「オーケイ、いま日本語のわかる人を呼ぶから大丈夫だよ」
連隊長は白人の副官に命じた。
「調達庁のウサミを連れてきてくれ」
やがて若い日本人が連隊長室に入ってきた。背筋をピンと伸ばし、連隊長に挨拶する。大野にも会釈する。
大野はウサミと呼ばれた男に、日本語で思いのたけを語った。
「ウチは貧乏やもんで、ぼくが働かんと食べていけないんです。だからどこかで仕事をして、学校には夜に通いたいんです。なんか仕事はないでしょうか」
ウサミはていねいに、大野の話を通訳してくれた。すると連隊長は笑いながらこう言った。
「そうか。お礼と言いながら、仕事を探しに来たか」
「イエッサー」
大野は通訳なしで答えた。
「じゃあ聞くが、その覚悟、ちゃんと両親には相談したのかい」
「イエッサー」
ウソだった。だけど力強く答えた。
「そうか。よし、わかった。ちょっと待って」
そう言って、再び白人の副官に命じた。
「倉庫係の曹長を呼んでくれ」
5分も経たないうちに曹長が「イエッサー」と言いながら入ってきた。黒人だった。
連隊長は言った。
「このボーイがどこかで働きたいと言ってるんだけど、おまえのところで引き受けてくれるか?」
「イエッサー」
曹長は、即答した。当然だ。連隊長に「ノー」とは言えない。
大野はドキドキしていた。(これはもしかしたら就職できるかも)
「ところでミスターオオノ、君はいくつだ?」
突然、連隊長が大野に聞いてきた。
「15歳です、サー」
「オー、15歳か。ウサミ、日本の労働法ってのは何歳から働けることになってるんだい」
ウサミは答えた。
「16歳です、サー」
あっ、と大野は思った。しくじった。16歳と言えばよかった。
連隊長室に一瞬、重い空気が流れた。その空気の膜を、連隊長が打ち破った。
連隊長は大野に近づくと、握手を求めてきたのだ。
「Congratulations !」
<おめでとう!>
しっかりと大野の手を握りながら、連隊長はそう言うのだ。
「Mr.Ohno , I give you special day !」
<ミスターオオノ、君にとくべつな日をプレゼントしよう>
「Your birthday is today ! So You are 16years old !」
<君の誕生日は今日だ。だからもう君は16歳だ>
大野は一瞬、意味がわからなかった。どういうことだ。今日が誕生日? つまり、連隊長はオレを16歳だと認めてくれたということか。このキャンプでは、オレは今日から16歳だ、と。だから働ける……。
「曹長、おまえいつから来てほしいんだ」
「いつでもいいです、サー」
「オッケー、ミスターオオノも準備があるだろう。よし、一週間後にまたいらっしゃい。なに、準備なんか何もいらない。替えの下着とか、それだけでいいからね。じゃあ一週間後、ゲートでオレの名前を言ってくれれば迎えを出すから」
そう言って、連隊長は片目を閉じた。
「ウィリアム中佐」
それが連隊長の名前だった。大野は『キャンプGIFU』に入れるパスを手にした。帰りは白人の副官がまたジープで送ってくれる。ゲートまでの間、副官は盛んに「おめでとう」と言ってくれた。そして「おまえはラッキーボーイだ」と。
大野は、達成感と幸福感に包まれていた。だが、その昂揚もゲートまでだった。
ジープを降りて、副官と別れ、衛兵にあいさつをしてゲートを出ると、現実が大野に向かって押し寄せてきた。
親にはなんて言おう。
学校はどうしよう。
先生にはどう言おう。
展開があまりにも早すぎて、大野は何ひとつ準備ができていなかったのである。
つづく
☆参考文献
『超訳 日本国憲法』池上彰 新潮新書
『ヴィダル・サスーン自伝』髪書房
『Vidal Vidal Sassoon The Autobiography』PAN BOOKS
『ヴィダル・サスーン』(DVD) 角川書店