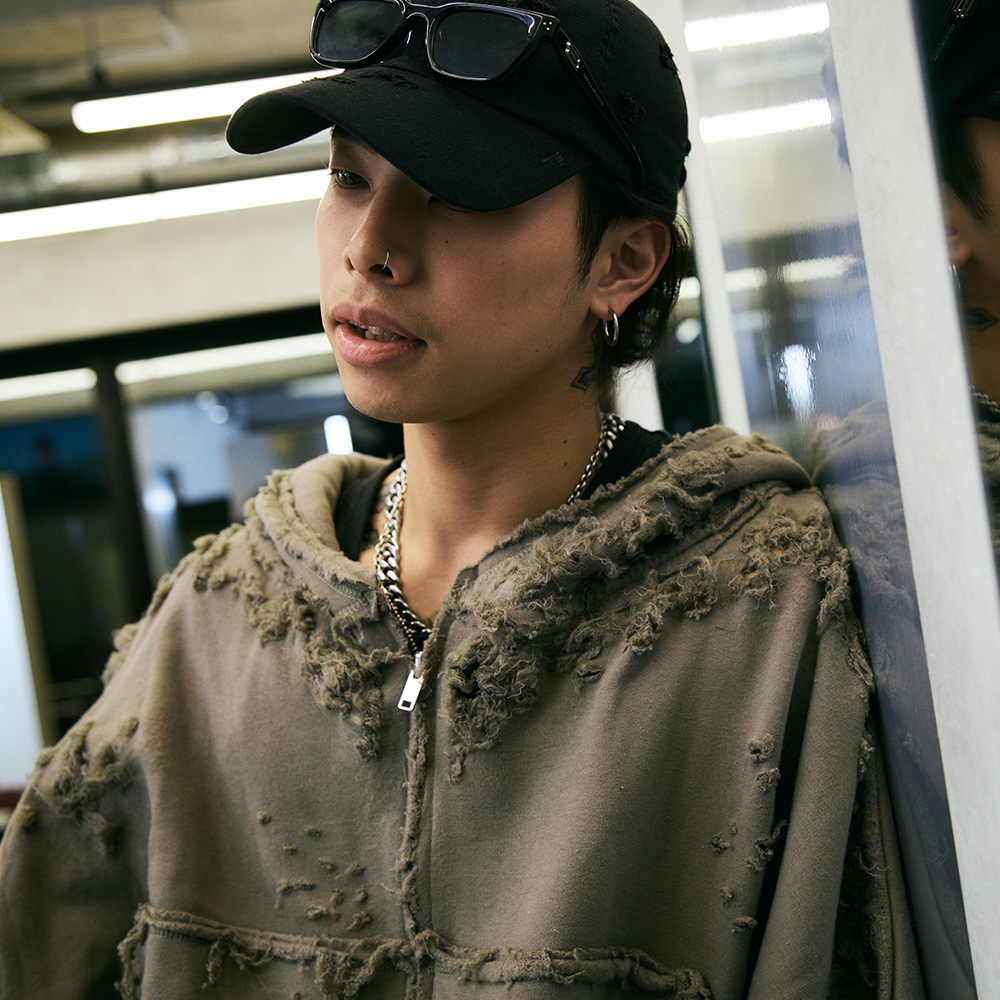【1970年 東京】
外国人の一行がロビーに現れたのは、午後3時を少し回ったころだった。
東京・日比谷の帝国ホテル。1970年初秋。
先頭にふたりの男。つづいて数人の女性たちが歩いてくる。みな長身で美しく、背筋がまっすぐに伸びていた。
女性たちは見たこともない頭をしていた。短く、まっすぐな髪。頭が動くたびにさらさらと髪も動き、頭が止まると髪も止まった。その女性たちに囲まれるようにして、笑顔で歩く男がいた。
あ、このひとだな……。大野芳男は直観した。
ちょうど1カ月前のことである。日比谷の三信ビルにあるBOAC(英国海外航空・現在の英国航空)日本支社。大野の上司で旅客部の部長だった相沢賢三が自らのデスクに大野を呼んだ。
「本社からテレックスが入りました」
相沢はメガネの奥から大野を見つめながら言った。小さくて細く、やさしい目である。
「来月、一等旅客でロンドンから重要なお客さまがやってきます。大野さん、アテンド(お世話)をお願いできますか」
相沢はいつもていねいな物言いをする人だった。部下の名前を呼ぶときも、必ず「さん」づけである。相沢は英文でびっしり埋まったテレックスのペーパーを大野に渡した。
一等旅客。今でいうところのファーストクラス。そのシートを利用して来日するお客さまは、これまでも少なからずいた。だがそれまで、上司からアテンドを頼まれたことはなかった。
いったいどんなVIP(重要人物)が来るっていうんだ。大野は興味津々でテレックスの英文に目を走らせ始める。その様子を見ながら相沢が言った。
「職業はヘアドレッサー。ま、美容師ですね。年収は18万5000ポンドというから、日本円にすれば1億6000万円になりますね」
えっ?
大野は思わず声を出していた。美容師って、あのパーマ屋の? それが1億6000万? どういうことだ。
1970年である。当時、大野の月給は2万5000円だった。12カ月で30万円。加えてボーナスが4カ月分で年収は合計40万円である。1億6000万円といえば、ちょうど400倍。よんひゃくばい……。つまりオレの給料の400年分。それを1年で稼いでいるというのか……。
大野は再びテレックスに目を走らせた。そこに記されたVIPの名前を、大野は読んだ。口のなかで。しかしそれはいつの間にか明確な声になっていた。
Vidal Sassoon
ヴィダル・サスーン
その『ヘアドレッサー(美容師)』が、やがて大野の人生を大きく転回させていくことになる。いやそれどころではない。その『美容師』は大野だけでなく、日本中の美容師たちの仕事を、人生を変えていくことになる。大野は結果的にその『革命』ともいうべきイノベーションの手伝いをすることになるのだが。
もちろんそのときの大野にとっては思いもよらぬことだ。とにかく今、命じられたのはその美容師のお世話をすること。
しかし、と大野は思った。
どうしてオレなんだ。会社には大卒の先輩や同僚がたくさんいるではないか。なのになぜ高卒のオレが……。
その疑問を、大野は相沢にぶつけてみた。
「部長、どうしてぼくなんですか。選ばれた理由を教えていただけますか」
すると相沢は答えた。
「英語ですよ。大野さんの英語はだれよりもこなれています。けっして美しくはありませんが、実用的です」
「はぁ。美しくはない、ですか」
「えぇ。まだアメリカなまりが抜けません。アメリカというより、大野さんの場合は米軍なまりでしょうかね」
そう言って、相沢は笑った。