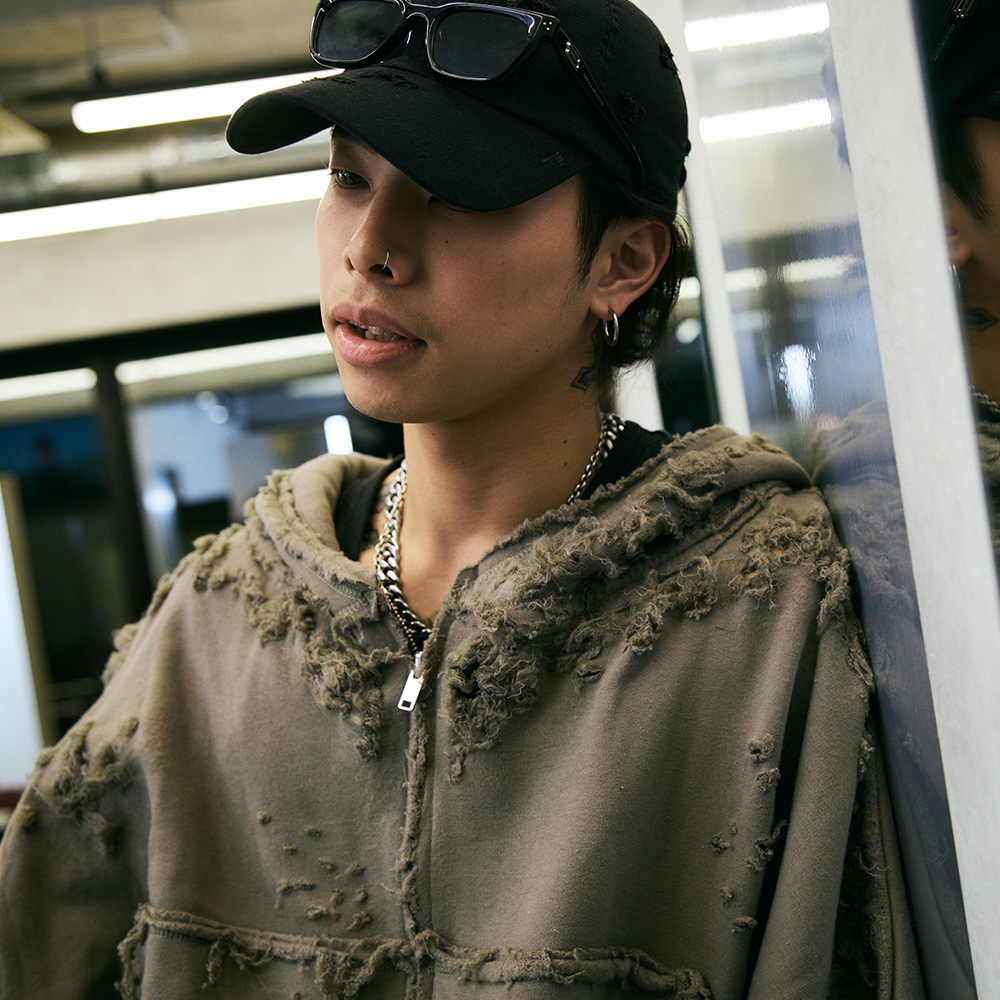召集令状が届いていた。
ある日、ヴィダルが自宅に戻ると、机の上に令状が置かれていた。
英国には徴兵制度があった。男子は18歳になると全員が兵役に就く。それは戦争が終わった後も継続していた。
ヴィダルに届いた令状は『The Royal Air Force』(英国空軍)からの招集だった。
令状が届いてから2カ月後、ヴィダルは基礎訓練を受けるためにロンドンを離れた。
身体を鍛えることは大好きだった。『43グループ』でも、時間を見つけてはジムを利用した。空軍の訓練所でも、ヴィダルはトレーニングを楽しんだ。
その日、ユダヤ人兵士全員に帰省が許された。
翌日は『ヨム・キプール(※)』。ユダヤ人にとって1年で最も重要な贖罪の日だった。それを家族で祝うことが許されたのである。
ヴィダルはロンドンに戻ると、母を連れてローダデール・ロードのシナゴーグ(※)へ向かった。そこはヴィダルが5歳から13歳までを過ごした孤児院が付属するシナゴーグだった。
ラビ(ユダヤ教の指導者・聖職者)が、ゆっくりと話し始めた。ヴィダルも、その日そこにいた参加者も、全員がその話に聞き入った。それは、いつものようなタナハ(旧約聖書)の話ではなかった。
「みなさん、ホロコーストのことはご存知ですね」
その最初の一言で、シナゴーグの空気が一変した。
「先日、私はそこから生還した方の話を聞くことができました。これからその方の話を、できるだけそのままお伝えします。どうか気持ちをしっかり持って、聞いてください」
会堂内は静まりかえった。
——————-生還者が語った話—————–
ヨーロッパのユダヤ人は、ある日突然、拉致され始めました。ナチスの親衛隊と警察が、ユダヤ人を家族ごと捕まえていくのです。
私は約80人が詰め込まれた貨物車両(貨車)に乗せられました。妻は別の貨車に、2人の子どもたちもまた別の貨車に乗せられました。
80人が乗った貨車というのは、どのようなものか想像できますか。ぎゅうぎゅう詰めでほとんどの人が座ることができません。横たわるなどもってのほかです。つまり立っているのです。それが4日間つづきました。昼も夜も列車は移動をつづけました。その間、与えられたのはパンが一切れ。
貨車の片隅にほんの少し、藁が積まれている場所がありました。当初、そこはまさしく天国に見えたものです。あぁ、あの藁の上に寝転ぶことができたら。そうしてぐっすりと眠ることができたら。
だけどそれはまさしく夢でした。その藁は、80人の排泄物をたっぷりと吸った“ベッド”なのでした。
それは5日目の明け方でした。列車は突然、不気味なブレーキ音を響かせたのでした。どこかに停まる。どこかに着いた。
どうやらかなり大きな駅のようでした。
私は列車が軍需工場に向かっているのだと信じようとしていました。軍需工場で、強制労働をさせられるのだ、と。そう信じないと、精神が持たなかった。あの、悪名高き強制収容所ではない。絶対にない。そう自分に信じ込ませようとしてきました。
しかし、貨車の中でだれかが叫んだのです。
「アウシュヴィッツだ」
その男は貨車の、板張りの壁の隙間から外の様子をうかがい、駅名の看板を見つけたのでした。
『ガス室』の噂は知っていました。『焼却炉』の存在も。ナチスはユダヤ人を大量殺戮している。そのおぞましい情報はつねに、分かちがたく『アウシュヴィッツ』という名前と結びついていました。
絶望が襲いました。
私はひしめく人々を押しのけるように壁へとにじり寄りました。小さな隙間を見つけると、ぶつけるように片目を当てます。
見えたのは、何重にも重なる鉄条網の壁でした。その上には監視塔。周囲を刺すように動きつづけるサーチライト。
突然、がらがらと鈍い音を立てて貨車の扉が引き開けられました。同時に、スキンヘッドの男たちが数人、中に入ってきます。着ているのは縞模様の服。囚人服のように見えたので、この人たちも収容されているのだとわかりました。
“囚人服”の男たちは元気でした。暗さも、悲惨さも、憔悴もありません。顔の血色はよく、痩せてもいません。あぁ、収容所生活もそんなに悪くないんだ。そんな気持ちが一気に湧き起こりました。ところがそれは大きな間違いでした。
あとでわかったことですが、彼らは「カポー」と呼ばれる“エリート”でした。収容者の中からナチスの親衛隊が選び出した“エリート”。とりわけ暴力的で犯罪者的性向のある者が選ばれ、衣食住の特権を与えられる代わりに親衛隊の下部組織として働く。そんな構図ができあがっていたのです。つまり、ユダヤ人をユダヤ人が監督する。しかもカポーは、ユダヤ人同胞に好んで暴力をふるいます。親衛隊よりもさらに激しく殴りつけるのです。
貨車に入ってきたカポーたちは、私たちの荷物を奪いました。収容所生活で何かの役に立つのではという、かすかな期待を込めた荷物。服や靴。日用品。現金や宝石、貴金属などの財産。それらすべてを剥ぎ取っていくのです。へらへらと笑いながら。
荷物を奪われた私たちは、貨車から降ろされました。新鮮な空気を胸一杯に吸い込もうとした、その瞬間に命令が下ります。
「男女別々に一列になり、親衛隊の将校に向かって歩け!」
将校はドイツ軍の軍服の上に厚手のコートを羽織っていました。背筋をピンと伸ばして立ち、左手で右手の肘を支えていました。両手は黒い革の手袋で覆われ、肘を支えられた右手は将校のあごに添えられています。
将校の前に最初の収容者が到着しました。すると将校はその収容者を見つめ、右手をあごから離して人差し指を動かします。後方の私の方から見て、左へ。その指示に従って、収容者は左へと進みます。次の収容者も左。その次も左。たまに右へ進む収容者もいましたが、後方から見ていると左へと進む人が圧倒的に多かったのです。左、左、左、右、左、左、左、左……。
やがて私の子どもたちが、将校の前に立つのが見えました。
“あぁ、無事だった”
私は安堵しました。
7歳の長男は左でした。4歳の次男も左。見ていると小さな子どもは全員が左でした。
私の番がやってきました。妻はまだ私の後方で順番を待っているようです。私はもちろん左を希望していました。せめて子どもたちの側にいてあげたい。だから頼む、左を指してくれ。
右でした。私は子どもたちと離ればなれになったのです。
右へと行かされた私は、“消毒”のために控え室で待たされていました。親衛隊員がそこへやってきて、大きな布袋を拡げました。
「持ち物はすべてここへ投げ込め」
例外は許されませんでした。身につけていたものすべてが剥ぎ取られました。結婚指輪も、家族の写真入りのロケットペンダントも。
それから私たちは隣の部屋に追い立てられました。そこにはもうひとりの親衛隊員がいて、叫んだのです。
「2分だけやる。着ているものを全部脱げ。始めっ」
全裸になるのです。文字通り、全裸です。今、我が身に起こっていることをどう解釈すればいいのか、全くわかりませんでした。しかし親衛隊員は考えるヒマを与えません。全裸になった私たちが次の部屋へ追い立てられると、今度は毛を剃られました。髪の毛だけではありません。身体中の毛という毛をすべて。
それからシャワー室でした。
私は再び絶望しました。あぁ、終わった。そう思いました。私の人生はここで終わる。シャワーのノズルからは毒ガスが出てきて、私は殺される。
そんな噂は私たちユダヤ人の間でしっかりと共有されていました。
“『入浴施設』には気をつけろ。そこはガス室だ”
身体中の毛を剃られ、全裸になった私たちは親衛隊員に殴られたり、小突かれたりしながらシャワー室の中へと追い立てられました。全員が中に入ると、シャワー室の扉が閉められました。
ガタン。扉が閉まる大きな音。ひしめき合う全裸・禿頭の男たち。頭上を見上げると、くすんだ灰色のノズル。それは天井と私たちの頭との間に、何列にもわたってぶら下がっていました。
ぶつぶつと小さな穴がたくさん空いた丸いノズルが、私をじっと見ていました。私はもう何も考えていませんでした。ただ目の前にあるノズルを、その小さな穴を見つめ返すだけでした。
ガクン。再び大きな音が聞こえました。同時に、モーターが回るような音がしたその直後。
水が出ました。ノズルからは水が飛び出ました。極寒のなかの、水シャワー。それでも私たちは跳び上がるほど喜んだのです。毒ガスではなく、本物の水が出たのですから。
その後、左腕に入れ墨が施されました。彫られたのは識別番号です。1390842。それが私の番号でした。以来、私たちはつねに番号で呼ばれ、番号で認識されることとなりました。つまり私たちは名前すら、剥ぎ取られたのでした。
入れ墨が終わると、ようやく服が配られました。あの縞模様の“囚人服”でした。
宿舎は木製の板でつくられた、隙間だらけの小屋でした。そのなかに3段ベッドがびっしりと並びます。
ベッドの大きさは縦2mほど。幅は2.5mほどあったでしょう。通常のベッドよりも幅がかなり広くとってあります。その理由は就寝時刻になるとわかりました。1段に9人が寝るのです。つまり3段ベッドは27人の寝床だったのです。しかもそのベッドにはマットがありませんでした。毛布もありません。板敷きの“ベッド”に、9人の男たちが身体をぴったりと密着させて寝るのでした。
就寝前に、ほんの少しだけ時間がありました。部屋には私たち新入りを待ち受ける“ベテラン”収容者もいます。私はそのひとりに、ずっと気になっていたことを聞いてみました。
「最初、親衛隊の将校に右と左に分けられますよね。あのとき左に行った人はどこにいるのでしょう」
「おまえさんは、右だったのか」
「はい」
「じゃあ右がこの強制労働棟だ」
「左は? およそ9割の人たちがそっちへ行きましたけど」
「ふん」
そう言って、その“ベテラン”は私の目をのぞき込みました。
「左に行かされたヤツのなかに知り合いでもいたのか」
「あ、はい。まぁ……」
知り合いどころではない。私の大事な、かけがえのない子どもたちだ。
“ベテラン”はおもむろに立ち上がり、窓のそばまで行って私を招きました。
「ほら、あそこに煙突が見える」
真冬の夜。外は真っ暗でした。だけど、煙突の存在はわかりました。百メートルほど先に、空に向かって赤い炎が勢いよく吹き出していたからです。
「おまえさんの知り合いは、いま、まさにあそこから天に召されている」
しばらくの間、私にはその言葉の意味がわかりませんでした。呆然と遠くの炎の柱に見入っていると、“ベテラン”は教えてくれたのです。
「9割が向かった左側は、病人や労働不適格者が行く道だ。つまり、淘汰の道。それはガス室から焼却炉へと……」
叫んでいました。最後まで聞いてはいませんでした。私は叫びながら、ドアへ向かって駆けました。カギのかかったドアに、体当たりをしました。しかし開きません。つづいて私は窓へ向かいました。それまで、私の行動を黙って見ていた“ベテラン”が、ようやく動きました。駆け出す私に、足をかけて転ばせたのです。次の瞬間、数人の男たちが私の上に馬乗りになっていました。
「窓を壊されちゃ、かなわんからな。このくそ寒い夜に」
私はそれでも叫びつづけていました。あそこには私の子どもたちがいる。子どもたちが焼かれてしまう。
いきなりドアが開いて、カポーたちが入ってきました。手に持った棍棒を振り上げ、私を殴りつけます。それでも私は叫んでいました。痛みも何も感じませんでした。つづいてやってきたのは親衛隊員でした。私はその軍靴が、私の身体にめり込む様子を見ながら、視界を失ったのでした。
どのくらい気を失っていたのでしょう。目を開けようとしても、まぶたは重く開きません。ほんの少し、見えたのは土の床でした。どうやら私は土の床の上に転がされているのでした。
そのとき、私は「私が生きている」ことに気づきました。次の瞬間、再び感情が爆発しました。あの煙突に行かなければ。子どもたちを助けなければ。
だけど身体はぴくりとも動きませんでした。
涙があふれていました。腫れ上がったまぶたの隙間から、涙があふれていました。
こころのなかは深い、ふかい絶望で塗りつぶされていました。私は氷のように冷たい床にうつぶせになり、片頬をべったりと土に貼り付けながら絶望を見つめていました。
涙は、あふれつづけていました。
“神よ、わが主よ”
その先の言葉が、見つかりませんでした。わが主はどのような理由で、私たちにこのような地獄に放り込んだのでしょう。私には考えられませんでした。考える力を、失っていました。
“絶望”のなかに、赤いものが動き始めたような気がしたのは、それからずいぶん経ったときでした。
部屋にはだれもいないようでした。みな、労働にかり出されているのでしょう。私はすでに立派な「労働不適格者」でした。私もすぐにあの煙突の下に連れて行かれる。子どもたちのそばに行ける。そう思っているのに、私の“絶望”が動きます。どす黒い塊の表面が、対流するかのような動きを始めます。その流れの間に、ちらっと赤黒い筋が見える。そんな気がしました。
私はこころの眼をこらして、その赤い筋を見つめました。するとその赤黒い筋は、みるみるうちに太くなります。同時に、私の意識が覚醒し始めました。意識は、私の感情に気づきました。
“憎悪”でした。“絶望”のなかの赤黒い筋は“憎悪”でした。私のなかに“憎悪”が渦巻いている。気づいた途端、なぜか力が湧いてきました。“憎悪”はますます燃え盛り、いつの間にか真っ赤になって“絶望”を凌駕していきます。
「くそっ」
何本も折れた歯の間から、声が洩れました。その声を、つぶれた耳で聞いた瞬間、私のなかでなにかが弾けたのです。
「生きてやる」
言葉が別の生き物のように滑り出します。
「生きて、復讐してやる」
「ヤツらを地獄の底に叩き込んでやる」
力が湧いてきました。涙は、もうあふれてはいませんでした。それよりも立ち上がること。立ち上がって、身体を動かすこと。絶対に「労働不適格者」にはならないこと。
こうして私は、真っ赤な“憎悪”のちからで、死と絶望の淵から生還したのでした。
————-生還者が語った話(終)—————–
ヴィダルの身体はふるえていた。ガタガタと音を立ててふるえていた。抑えの効かない怒り。噴き上がる憎悪。あの、ハロッズの隣のサロン『ヘンリ』を飛び出したときから飼っている“憎悪”が、再び蠢き始めていた。
長い話を終えたラビが、静かに言った。
「この方はその後、過酷な労働に耐え、収容所生活を最後まで生き抜きました」
「だが、お子さんたちと奥さまとは再会できなかったということです」
「先日、この方はパレスチナの地へ渡りました。イスラエル建国の戦いに、参加するために」
イスラエル建国の戦いは、19世紀から始まっていた。
しかし、第二次世界大戦が終わっても、イスラエルはまだ[建国]されてはいなかった。聖地・エルサレムを含むカナンの地(パレスチナ)は英国の委任統治領だったが、英国はユダヤ人の受け入れを制限していた。一方、先住していたアラブ人は民族主義に目覚め、入植してくるユダヤ人を迫害し始める。混迷する状況に、英国はなんら有効な策を打ち出すことができなかった。
ローマ帝国に滅ぼされて以来、イスラエル建国は2000年にわたってつづく悲願だった。ユダヤの若者はアラブ人から同胞を守り、一日も早く安住の地を確立しなければならない。ホロコーストの悪夢が明らかになるにつれて、そんな気運が急激に高まっていた。
合い言葉はひとつ。
“願うなら、それは夢ではない”
ヴィダルは決めた。
“パレスチナへ行く。イスラエル建国のために戦う。そうだ。それがぼくの使命なのだ”
だが、すぐに向かうわけにはいかなかった。ヴィダルの兵役は、まだ始まったばかりだった。
つづく
※脚注
【ヨム・キプール】Yom Kippur
贖罪の日。ユダヤ教における最大の休日のひとつ。前日の日没から当日の夕方まで、労働はもちろん飲食も入浴も化粧も禁じられ、シナゴーグで祈りを捧げる。
【シナゴーグ】Synagogue
ユダヤ教の会堂。タナハ(旧約聖書)の朗読や解説を行う集会所。キリスト教でいう『教会』の前身。
☆参考文献
『ヴィダル・サスーン自伝』髪書房
『Vidal Vidal Sassoon The Autobiography』PAN BOOKS
『ヴィダル・サスーン』(DVD) 角川書店
『夜と霧』ヴィクトール・E・フランクル著 みすず書房
『イスラエル建国の歴史物語』河合一充著 ミルトス
『私家版・ユダヤ文化論』内田樹著 文春新書
『アメリカのユダヤ人迫害史』佐藤唯行著 集英社新書